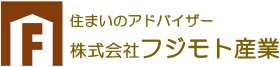飲食店舗が次々と閉店していく・・・
最近、人口増加が著しい弊社の地元
(大阪市天王寺区・中央区の玉造、鶴橋、森ノ宮、上本町周辺)でも
飲食店舗が次々と閉店していく姿を目にします。
かつてお客様で賑わっていたお店が突然シャッターを下ろす。
その光景は、地元で暮らす私たちにとって非常に寂しいものです。
実際、私も通っていた喫茶店が連日常連客で賑わっていたのですが、先日閉店しました。
いつものコーヒーの香りが漂う空間がなくなり、ぽっかりと心に穴が空いたような気分です。

飲食店閉店の背景
閉店前、喫茶店のオーナーと話し合う機会がありました。
理由は非常にシンプルでありながら深刻なものでした。
「コーヒー豆や原材料の高騰」
「光熱費の値上げ」
「人件費の上昇」
「人手不足」
これらが主な要因です。
この値上げ分を価格に転嫁できないのが厳しいともおっしゃっていました。
最近のインフレは私たち消費者にも大きな影響を与えていますが
店舗経営者にとってはさらに厳しい現実です。
例えば少し前なら安定して仕入れられた材料が、今や価格が倍以上に跳ね上がることも珍しくありません。
また、電気代やガス代の負担増加も、特に飲食店にとっては死活問題です。
さらに人手不足の問題も深刻です。
アルバイトや正社員の採用が難しくなり、営業を維持すること自体が
困難になるケースも多いそうです。
魅力的な街並みが広がるエリアでありながら、このような閉店の波が
押し寄せている現状を考えると、どこか胸が痛みます。
地元にとっての飲食店の役割
飲食店は、単に食事を提供する場ではありません。
それは、地域の人々が集まり、交流し、日々の生活に潤いを与える大切な場所です。
私も喫茶店で過ごす時間が日課でした。
そのお店ではスタッフの方と顔見知りになり、他のお客さんと世間話をすることもありました。
それが日常の「ひとコマ」だったのです。
しかし、こうした店舗が姿を消していく中で、街の風景や雰囲気にも少しずつ変化が生じています。
飲食店がなくなることで、人々が集まる場所が減り、街の活気そのものが失われていく気がしてなりません。
地方でも同様に、以前はどんな小さな田舎町でも、駅前には喫茶店や食堂がありました。
昭和40年代から50年代の初めの頃、私は学生でしたが
北海道の最果ての田舎町にあった食堂でラーメンを食べ、列車を待つ時間は喫茶店で時間をつぶして
旅のプランを練ったり、地元の人たちと雑談したりした楽しい思い出があります。
喫茶店は地元のおじさんやおばさんのコミュニティの場所になっていました。
今思えば懐かしい光景ですが、飲食店がこのような社会的貢献をしていたことを今更ながら感じる次第です。

未来への希望と地域の力
とはいえ、希望がないわけではありません。
このような状況下でも、新たに挑戦する店舗も少しずつ増えています。
地域住民として、どうすればこうしたお店をサポートできるのか?
一緒に考えていくことが求められています。
こうしたお店で地元の人たちが積極的に食事をしたり買い物をして支えていくことは
ひいてはその市域の町の発展にもつながっていくのです。
また、SNSを活用してお気に入りのお店を応援するなど
小さなアクションが店舗経営者にとって大きな励みになるでしょう。
大阪でも上町台地は歴史と文化が豊かで、人々の温かさに溢れた場所です。
玉造、森ノ宮、鶴橋から谷町、上本町にかけて、その魅力を支えるのは、間違いなく地元の飲食店や小売店です。
こうしたお店を地域で支えていくことが、魅力あるまちづくりに大きく貢献することだと思うのです。
魅力的な街には人が集まり、経済も活性化する。これは疑う余地がありません。
『国際都市大阪』のまちづくりに貢献
大阪は近年、外国人旅行者が飛躍的に増えてきています。
その証拠に国際都市の魅力ランキングでも、年々順位を上げてきています。
我々大阪人としてはうれしい限りです。
今後どの程度順位を上げていくか楽しみです。
大阪は今から30年前のバブル期は、地価こそ急上昇しましたが、魅力的と言うにはほど遠く
外国人はおろか日本人旅行者からも見向きもされなかった時代がありました。
関西へ旅行しても「京都と神戸のみ、大阪は見るところがないのでスルーする。」
こういう方がとても多かったように思います。
残念ながら、外国人における知名度も極めて低い時代でした。
40年前に私が欧米を旅行した際は、日本の都市で一般的に知られている都市と言えば
東京・広島・長崎の三都市で、大阪といってもほとんどの人が知りませんでした。
現在、国際的にも大阪の知名度は大きく上がってきているようです。
今後、ますます魅力ある街にするために飲食店舗をはじめとしたお店で
賑わう街が形成されることを期待したいものです。