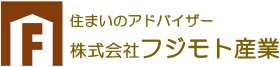両親の他界とともに思わぬ厳しい現実に直面
あるセミナーで、弁護士が語った実話があります。
先祖代々受け継がれてきた飲食店を父親から引き継いで長男が経営していました。
長男には3人の兄弟姉妹がいましたが、両親が引退した後も長男夫婦は
この自宅兼店舗を守り、日々の営業を支え続けてきました。
特に両親が高齢で健康を損なってからは、長男の妻が病院への付き添いや介護など
日常の世話を献身的に行い、最期まで面倒を見続けてきました。
やがて父親が他界し、続いて母親も亡くなった後、相続の問題が浮上しました。
長男の兄弟姉妹たちはそれぞれ独立し、自宅を所有しており
普段はほとんど実家に顔を出すこともありませんでした。
しかし、この実家はまだ母親の名義のままでした。
そして、母親が亡くなった後、彼らは突然
「実家を売却して現金化し4人で均等に分けるべきだ」と主張し始めたのです。

法律は平等のはず・・・しかし、実態は不公平
法律では、民法に基づいて親の財産は子どもたちが均等に分けることが
定められています。
しかし、長年にわたり長男夫婦が店を切り盛りし、両親を献身的に
看取ってきた事実は、兄弟たちの主張には一切考慮されませんでした。
長男夫婦は、両親の介護や家業の運営に多くの時間と労力を割いてきたため
経済的には余裕がなく、自分たちの財産もほとんど持っていませんでした。
そのため、兄弟たちの要求に応じて自宅兼店舗を売却し、現金化するほか
方法はありませんでした。
これにより、長男夫婦は生活の場だけでなく、生計の基盤である仕事も失うこととなったのです。
これまでの努力や献身が認められない無情な現実に、長男夫婦はただ呆然とするばかりでした。
弁護士に相談するも 「時すでに遅し」
こんな中、長男夫婦は途方に暮れ、このセミナーを開いた弁護士に
相談に来ましたが、時すでに遅しでした。
もしこれが長男の母親の生前であれば、遺言書を作成することで
このような悲惨な事態を防ぐことができた可能性が高かったのです。
長男夫婦が母親に
「死後も私たちがこの自宅兼店舗に住み、商売を続けられるように遺言書を書いてほしい」
と相談していれば、おそらく母親は快く応じてくれたでしょう。
この場合、たとえ相続の段階で兄弟姉妹3人が遺留分を主張したとしても
長男の所有権は8分の5を保持でき、実家の売却に至るような事態は回避できたでしょう。
しかし、現行の民法の下では、長男夫婦が両親の介護や家業の維持に費やした労力や費用は
遺産分割の際にほとんど考慮されません。
これは「親の面倒を見るのは子どもとして当然のことであり、その労力や費用を
兄弟姉妹に請求するのはおかしい」という理屈に基づいています。
現実を見てみると、両親のもとで育った兄弟姉妹たちは、最終的に介護の負担を
長男夫婦に押し付けていたのです。
親の介護には肉体的な疲労だけでなく、精神的なストレスや日常の犠牲も伴います。
それにもかかわらず、その労力や費用が全く評価されずに相続分が均等に分配される
という事実はなんともやりきれない気持ちになります。
遺言書さえあれば、こうした不公平や争いは避けられたはずです。
両親が健在の時に話し合っていれば・・・
このケースでは、本来であれば長男夫婦が両親の元で家業を継いでいる間に
将来、両親が亡くなった後の事業の継続や住居について話し合う機会は十分にあったはずです。
その時点で両親が
「長男夫婦に後を継がせるので、家も長男夫婦に相続させたい」
と意向を兄弟姉妹に伝え遺言書を作成していれば、このような事態は避けられ
兄弟姉妹も納得してもっと円満に解決できたと思います。
亡くなった両親としては、自分たちの死後は兄弟姉妹が話し合いを通じて
円満に解決できると考えていたのかもしれません。
しかし、現実には民法の規定を杓子定規に主張する兄弟姉妹がいたのです。
法律は平等である一方、実態は不公平なものでした。
こうした負担を引き受けてきた長男夫婦が報われることなく、財産分配に巻き込まれることは
親の介護をするのは馬鹿馬鹿しいという風潮にもつながりかねません。
こうした場合にも備え、遺言書を準備しておくことは、家族の絆を守り
公平な相続を実現するための重要な一歩です。